裁判官の立場から見た共同親権制度の課題と展望―共同親権制度の導入とその選択的運用に関する見解

1 はじめに──裁判官が直面する「子の福祉」と選択的制度のジレンマ
共同親権制度が導入された背景には、「別居親を排除しない」「共同して養育責任を負う文化を醸成する」という立法的意図がある。
他方で、家庭裁判所の現場では、これまで親権と監護権の分離を否定してきた長い歴史がある。また、親同士の対立、信頼関係の崩壊、そして子どもの意思表明の困難さといった現実的課題が横たわっており、「制度がどうあるべきか」と「制度をどう使えるか」は、しばしば乖離し矛盾するものである。
制度の目的が「子の福祉の実現」にあることは論をまたない。しかしその「福祉」は、誰がどう評価するのか、どの声に耳を傾けるのか──家庭裁判所の判断において、説明責任と制度的公正さがより強く問われることになる。
2 共同親権が「選択制」であることの意味──任意の合意か、制度的要請か
改正法では、「共同親権を選ぶ」ことができるとされている。これは柔軟性の表れとも言えるが、同時に制度としての明確な価値判断を回避している側面も否めない。ひょっとして、知らない間に、「原則共同親権論」によることはできないと思われる。
選択的共同親権とは、裏返せば「共同養育が可能な関係であれば選べ、そうでなければ選べない制度」である。したがって、裁判所は常に「養育協力の可能性」と「現時点での関係の回復可能性」を判断しなければならない。そうでなければ、「非合意型の共同親権の強制」を憲法13条・14条や24条から正当化することが困難である。
とくに、DVや児童虐待が「除外事由」として明記されることは、諸外国でも当たり前のことであって、日本で問われるのは「選択的共同親権」の「除外事由」である。
これら、「非合意型」の「共同親権の強制」は、どの程度のこどもの最善の福祉への影響、頻度・態様・持続性・証拠水準で判断されるのかについては、運用に委ねられており、裁判官として極めて慎重な構造判断が求められる。
3 DV・虐待だけが除外理由なのか──モラハラ、恐怖支配、心理的支配への認知
家庭裁判所が直面する事案のなかには、「子どもに対する暴力はないが、配偶者に対する恐怖支配・威圧・人格否定があった」ケースが存在する。昔と異なり、現在では経済力や精神力による支配、つまりいわゆるモラルハラスメント(モラハラ)と呼ばれる行為に注目が上がる。
形式的な身体的暴力の証拠に乏しく、主張する被害者にとっては「再主張することそのものが再被害」である。
改正民法は、DVや児童虐待があれば単独親権とする建付けをとっているが、DVや虐待の存在を「有無」として評価するのではなく、継続的支配構造の有無や、意見形成の萎縮・自由な子育ての困難性を含めて「スクリーニング」として評価しなければ、オーストラリア法の二の舞になりかねない。
そして、制度は「形式的共同行使」の名のもとに、被害当事者に手続的苦痛の反復を強いることになりかねない。
4 「子の福祉」は誰がどう測るのか──制度と主観の狭間で
「子の福祉」という理念は、親の意向、生活実態、家庭環境、子の発達段階、意見表明の能力といった多様な要素の上に成り立っている。だが現場では、「子の福祉」は「親の都合」に摩り替えられ、「制度の安定性」が、それを代替してしまうこともある。
イリノイ州では、750 ILCS 5/600 et seq.(通称IMDMA)に基づいて、次のような原則が示されている:
- 通常、非監護親にもreasonable parenting time(合理的な親時間)が認められる。
- しかしながら、以下の場合には制限(restriction)が許容される:
“The court shall restrict parenting time… if it finds, by a preponderance of the evidence, that a parent’s exercise of parenting time would seriously endanger the child’s physical, mental, moral, or emotional health.”
つまり、親の面会交流を制限するには、「子の身体的・精神的・道徳的・感情的健康を著しく害する」ことが「証拠の優越(preponderance of the evidence)」によって証明されなければならないとされています。イリノイ州でも反証の程度はかなり広いことが分かります。
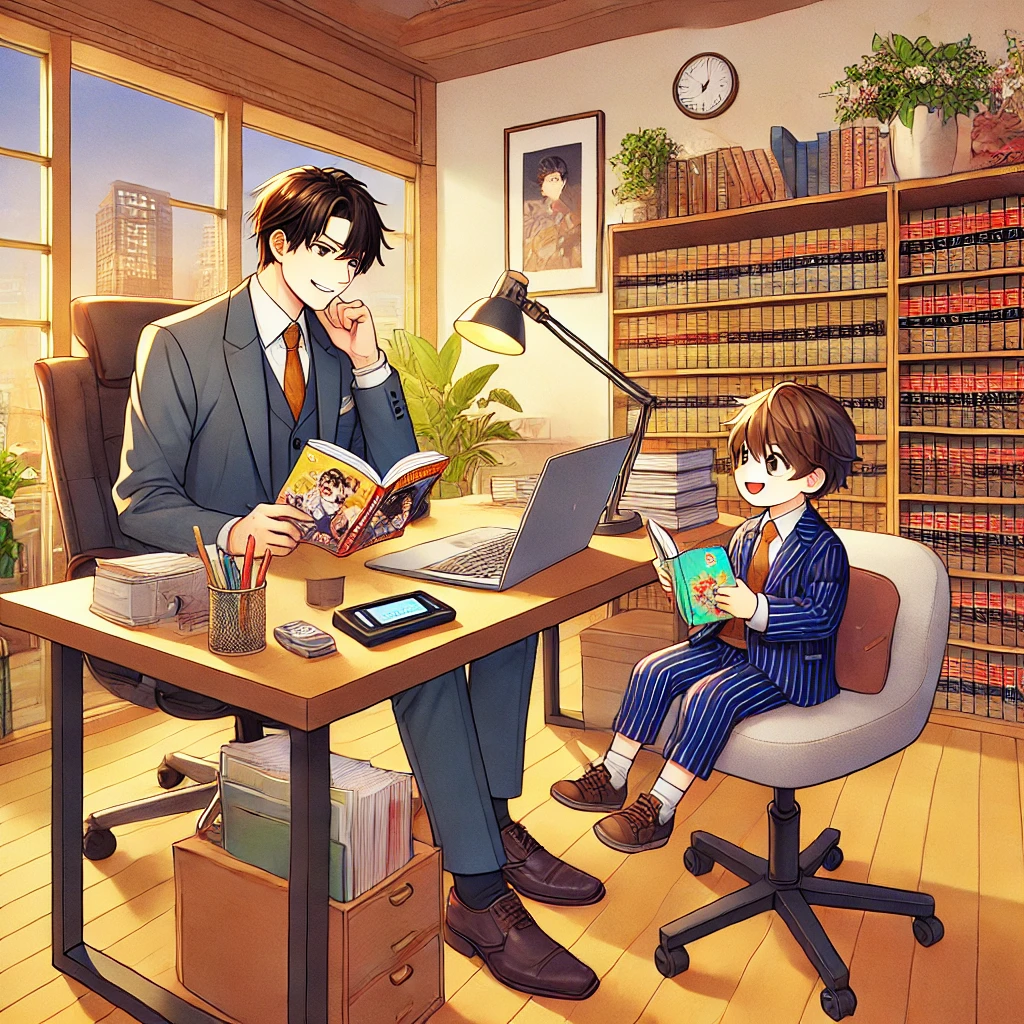
また、DVや児童虐待のスクリーニングに比較的成功していると思われるカリフォルニア州では、過去5年のDVや保護命令の前科がある場合は、その心配がないことの反証責任が課されるという立証責任の分配により、正義が保持されている側面も否定されない。
「元夫にもう生活を荒らされたくない」「調停の場に戻されること自体が苦痛」という発言が出るのは、調停手続そのものが当事者の尊厳や安寧を揺るがしていることの表れである。これはデュープロセスに反する。
裁判所が求められるのは、「子どもが今どのような環境にあり、何を望んでいるのか」に耳を傾けつつ、「親の一方に偏らない判断が子の利益にどうつながるのか」を文脈のなかで説明できる構造判断といえるかもしれないが、父母の協調という側面も見る必要がある。
5 「声を持つ子」としての子ども──制度の中でどう意思を形成させるか
法制審議会が強調した「子どもの意見表明権」や「最善の利益の優先原則」は、理念としては共有されている。しかし、子どもの声が制度的に保障されなければ、それは単なる象徴にとどまる。家裁調査官の10分から30分の局所的なこどもの意見に中身はなく「単なる象徴」に堕落している。
たとえば、家庭裁判所調査官による一度限りの面接や、形式的な聴取では、子どもが何を恐れ、何に配慮して沈黙し、あるいは希望を語れないかを把握するには不十分である。意見形成の過程において「支援者」としてのこどもの手続代理人弁護士や、民間の篤志家によるこどもアドボゲイト活動が必要であることは明らかであり、手続代理人の制度的活用は今後不可欠である。けだし、こども家庭庁の予算は7兆円であるが、裁判所は家裁を含む全体でたったの7000億円しかない。裁判所が専門化を雇うことは不可能であるのだ。
6 裁判所の責務──制度の設計と運用の間に立つ者として
制度は中立である。しかし、中立であるということは、無責任であることと同義ではない。
改正民法は共同親権を可能にしたが、それは裁判官の判断の自由裁量を広げたのではなく、判断の憲法的説明責任のみならず民主的統制としての責任を拡張したという理解が正しい。誰の意見がどのように尊重されたのか、なぜそのような結論に至ったのかを、当事者にも社会にも丁寧に説明することこそ、制度の正統性を支える唯一の方法である。
「原則実施」とスクリーニングの緊張関係
親子交流の「原則実施」説は、子の福祉を親の継続的関与によって支えるという理念に基づき、一定の理論的妥当性を有する。たしかに、アメリカ、カナダ、ドイツ、そしてオーストラリアにおいても、両親による継続的関係が子の発達にとって好ましいとする実証的・政策的基盤は存在する。
しかし、オーストラリア家族法制度において実際に問題となったのは、「原則実施」を形式的に導入しながら、DVや児童虐待リスクを十分にスクリーニングしないまま判断が下された事案が存在した点である(Rhoades, Graycarらの研究参照)。つまり、「原則」が理念として掲げられたことで、スクリーニングが形式的な確認作業に堕したという反省がある。その結果、こどもの適応にもネガティブであるといえる。
わたしは、同じく共同身上監護を掲げたオーストラリア法が失敗の象徴とされ、カリフォルニア州法は現在も残るのは、スクリーニングや立証責任の転換があったかの違いが大きかったと見ています。日本の面会交流原則実施説の失敗は、オーストラリア法の失敗と根底では共通しています。
この教訓を活かすには、単に「原則」を掲げるだけでは不十分であり、それが常に例外的配慮を要する子どもたちの現実をすくい上げる柔軟性と統合されているかどうかが問われる。
制度設計において本質的なのは、「原則」と「例外」の形式的線引きではなく、それぞれの子どもが“どのように制度の中で声を持ちうるのか”を前提とした設計であるかどうかである。
結語──Breyer判事の言葉による照射
スティーヴン・ブレイヤー判事はこう述べている:
“In the law, as in life, the most important truths are often found not in the rules, but in how we listen.”
(法においても人生においても、最も重要な真実は、ルールの中にではなく、私たちがどのように耳を傾けるかにある。)
すなわち、親子交流を「原則」として掲げるか否かよりも、その原則の下で、どれだけ一人ひとりの子どもに耳を傾ける制度が設けられているか──そこに、制度の正義が試されている。
親子交流の「原則実施」説は、子の福祉を親の継続的関与によって支えるという理念に基づき、一定の理論的妥当性を有する。たしかに、アメリカ、カナダ、ドイツ、そしてオーストラリアにおいても、両親による継続的関係が子の発達にとって好ましいとする実証的・政策的基盤は存在する。
しかし、オーストラリア家族法制度において実際に問題となったのは、「原則実施」を形式的に導入しながら、DVや児童虐待リスクを十分にスクリーニングしないまま判断が下された事案が存在した点である(Rhoades, Graycarらの研究参照)。
かかる失敗を犯したのは、細矢郁による「原則実施説」及び「ニュートラルフラットモデルも同様であり、DVや児童虐待でもエフピックを使えば良い、といった苛烈なものの結果、家庭裁判所は国民から信頼を失う結果とあった。多くの対抗言論を巻き起こしたのも実際はスクリーニング不足が大きいのではないか。
細矢郁『原則実施説』『ニュートラルフラットモデル』の失敗の教訓を活かすには、単に「原則」を掲げるだけでは不十分であり、それが常に例外的配慮を要する子どもたちの現実をすくい上げる柔軟性と統合されているかどうかが問われる。
制度設計において本質的なのは、「原則」と「例外」の形式的線引きではなく、それぞれの子どもが“どのように制度の中で声を持ちうるのか”を前提とした設計であるかどうかである。
すなわち、共同親権ないし親子交流を「原則」として掲げるか否かよりも、その原則の下で、どれだけ一人ひとりの子どもに耳を傾ける制度が設けられているか──そこに、制度の正義が試されている。
以上

